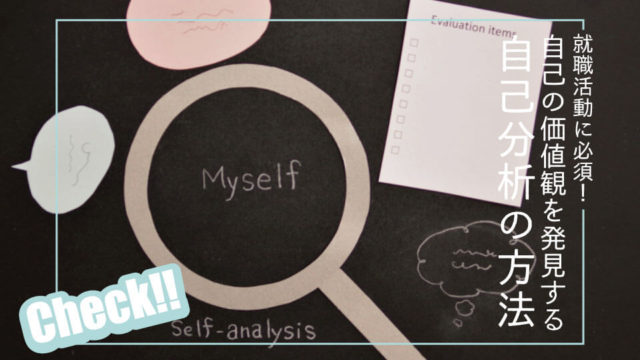アイキャッチ:fumika
挿絵:うみこ
こんにちは、るいるい(@Seayoumom1)です!
「ついに子どもがスマホを持ちたいと言い始めた。ルールはどうしよう?」
「自分で管理できるようになるまではスマホ買わないつもり。小学生ではまだ早いよね?」
という疑問やお悩みありませんか?
この記事では、これからお子さんにスマホを持たせる予定、またはお子さんのスマホにまつわる様々なトラブルにお悩みの保護者のみなさまに、スマホとの付き合い方を考える上で大切なポイントを紹介していきます。
ご家庭で方向性を決める際のヒントとなれば幸いです!
スマホを持たせる時のルールはどうしたら良いの?
いよいよ子どもにスマホを持たせる時期にきた保護者のみなさま。なんらかのルールは設けたいですよね。たくさんルールがあっても守れるか疑問だし、どこまで制限すればいいのか・・難しいところです。
スマホのルール、みんなはどうしてる?
既に、子どもにスマホを持たせているというご家庭ではどんなルールや対策があるのか調べてみました。
- 食事中は触らせない
- 大人の目の届く範囲で使わせている
- アプリ購入時などのパスワードは親が管理している
- インターネット利用状況などは親が見れるようにしている
- フィルタリングを使っている
など、子ども自身の所有物として与えているというよりも親が貸しているというスタンスをとっているご家庭が多い印象です。
「スマホ18の約束」が話題に
スマホ利用時のルールに関して、Twitterでは たけうち@speranza_911さんの投稿が話題になっていましたね。
娘が学校から貰ってきたプリント。
初めてスマホを持つお子さま、持たせる親御さんだけじゃなく全ての方に読んでほしい。 pic.twitter.com/NryZzVSTDC— たけうち (@speranza_911) 2018年11月17日
この「スマホ18の約束」、元はアメリカに住む当時13歳の息子に向けて母親が書いた手紙。彼女がブログにこの手紙の内容を転載すると、あっという間に世界中に広がり共感を呼びました。
その内容がこちら
母から子へ、スマホ 18 の約束
1.これは母がお金を払って購入したスマホです。 あなたに貸すだけです。
2. このスマホのパスワードは、常に母に知らせなさい。
3. これは電話器です。 着信音が鳴ったらマナーを守って「こんにちは」 と出なさい。
特に母や父からの電話は必ず出なさい。
4. 学校がある日は夜7時半に、 週末は9時にスマホを母に返却すること。友達の親が出るから固定電話で連絡したくない………そんな友達には電話もメールもしないこと。
5.学校にスマホを持って行かないこと。 メル友とは直接会話をしなさい。 直接会話することは、生きていくためのスキルです。
6. 水没、破損、紛失の際の諸費用は自己負担です。お小遣いを貯めておきましょう。そういう事態は必ず起きます。 準備しておきなさい。
7.嘘をついたり、人を馬鹿にしたり、人を傷つけるだめに、このテクノロジーを使わな…いこと。人を傷つけるような会話にも参加しないこと。
8. オフラインで言えないようなことを、メールなどで送信しないこと。
9. 友達の親の前で言えないようなことを、メールなどで送信しないこと。
10. ポルノ禁止。母と共有できるような情報だけをウェブで検索しなさい。何か分からないことがあったら、 誰かに聞きなさい。母か父に聞くのがよいでしょう。
11. 公共の場所にいる時や誰かと話している時は、 電源を切るかマナーモードにしておくこと。
12. あなた自身や他の人のわいせつ画像は送受信しないこと。そのような行為はあなたの人生を破壊します。 インターネットはあなたの想像以上に巨大です。一度でもわいせつ画像を送信したら、 削除は不可能です。
13. 写真やビデオばかり撮りまくらないこと。生活のすべてを記録する必要はないのです。肌身で感じて、あなた自身の記憶にとどめましょう。
14. 時々はスマホを家に置いて出かけなさい。スマホ無しで生活できるスキルも身に付けましょう。
15. あなたの世代は史上最も多くの音楽にアクセスできるのです。 時々は、友達や周囲の人とは違う音楽をダウンロードして触れましょう。
16. 言葉を使ったゲームやパズル、知的なゲームを積極的にプレイしなさい。
17. 周囲で起きているいろいろなことを、あなた自身の目で見なさい。鳥の声をあなた自身の耳で聞きなさい。自分の脚で歩いて、 知らない人とも会話しなさい。 グーグルに頼らずに悩んでみなさい。
18. あなたはこのスマホで失敗するかもしれません。その時はスマホを没収します。 そしてその失敗について一緒に話し合って答えを出して行き、 またはじめからやり直しましょう。母もあなたのチームの一員です。
一方、Twitterでは約束の内容に関して「縛りすぎでは?」などの批判的な意見も多く見られました。
子どもの性格や親子関係、様々な状況によって価値観も変わってくるので「万人に適応するルール」というのは存在しないのかもしれませんね。
もう少し自由に使わせてもいいとする意見で、「父からの秘密の助言書」を公開されていた打村明(@akirau)さんのブログが参考になったのでご紹介します。
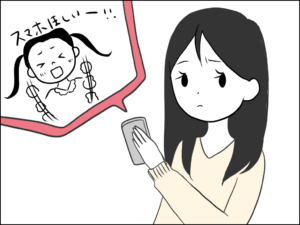
スマホはいつから持たせる?みんなは何歳から持ったの?
さて、そもそもいつ頃からスマホは持たせていいのか?
最近は小学生でもスマホを持っている子が多いようです。
内閣府の調査によると、小学生全体の約3割がスマホを持っているという結果に。
出典:平成29年度青少年のインターネット利用環境実態調査(内閣府)
*調査結果はこちらから→平成29年度青少年のインターネット利用環境実態調査
「小学生」部分を拡大します↓(青線がスマートフォン)
(拡大)青少年のスマートフォン・携帯電話の所有・利用状況
こちらは「小学生全体」なので「小学校高学年」に限るともっと割合は増えるでしょう。
周りが持ち始めると流れに従わざるを得ない状況もあると思います。マンガやテレビ、ゲームやファッションなども似たような現象になりますよね。
とはいえトラブルに巻き込まれる不安はどうしてもつきまといます。
最初から機能制限が備わっているスマホを選ぶこともできますし、フィルタリングのアプリをインストールするなどして、心配のタネを減らしましょう!

子どものスマホとの付き合い方は子育てに直結する!
みなさん感じているかもしれませんが、子どものスマホとの付き合い方は家庭によっても全然違いますね。
親自身がどのようにスマホを利用しているか、子どもの興味関心や性格、家庭での教育方針など・・それぞれの家庭の状況に落とし込んで、じっくり考える必要がありそうです。
すなわちスマホ問題は子育てを振り返るキッカケになるのではないでしょうか。
普段から親子の会話がありますか?
スマホでLINEなど友達とやり取りをするようになる、インターネットで色々なサイトを見るようになる、その時に心配なのがトラブルに巻き込まれることです。
どれだけ気をつけていてもその可能性をゼロにはできません。
大切なのは、何かトラブルが起きたとき親にすぐ相談できるかどうか。誰にも話せず一人で抱え込み、問題が大きくなることが一番こわいですよね。
普段から悩みや心配事を話せる関係性が作れているか。今いちど振り返っておきたいものです。
自己決定できる子に育てるために必要な事
小学生ならある程度、親の管理の範囲内で使わせることが可能でしょう。
しかし、成長とともにルールで縛ってばかりでは子どもも反発しますし、いつまでも親が干渉していては子どもも自己管理ができなくなってしまいます。
危険性や自己発信の責任を理解した上で、どのような情報をとり、どのようにリスクを回避していくか。子ども自身が判断して決めていく必要があると感じます。
子どもを信じること。
簡単なようで難しいですよね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
大人も簡単に依存してしまうスマートフォン。良いところも悪いところも理解した上で上手に付き合っていきたいですよね。
そのためには親である私たち自身のネットリテラシーも上げていきたいところ。このサイトでは親子で学べるネットリテラシーに関しても記事を増やしていきますので是非チェックしてくださいね!
「じゃあうちはどんな風にしようか」とご家庭での話のキッカケになってくれたら嬉しいです。