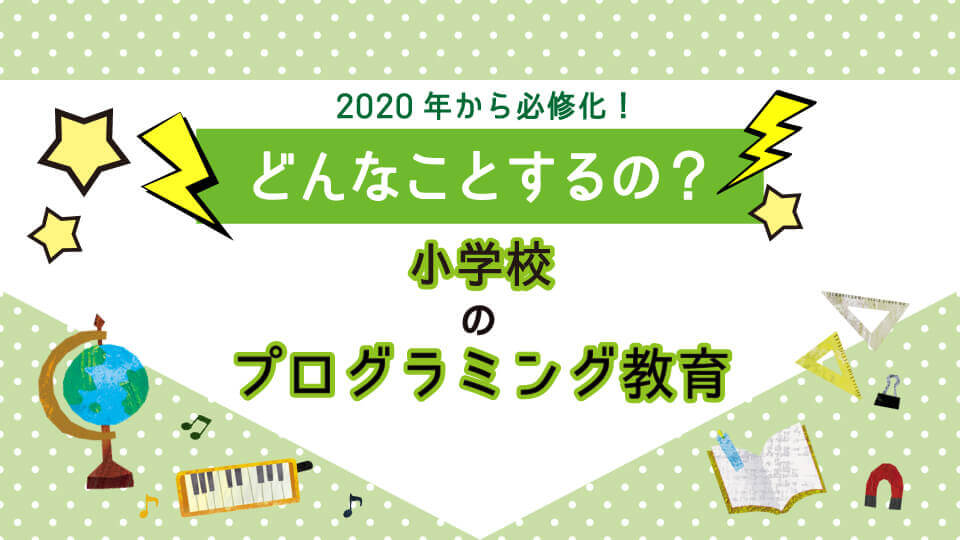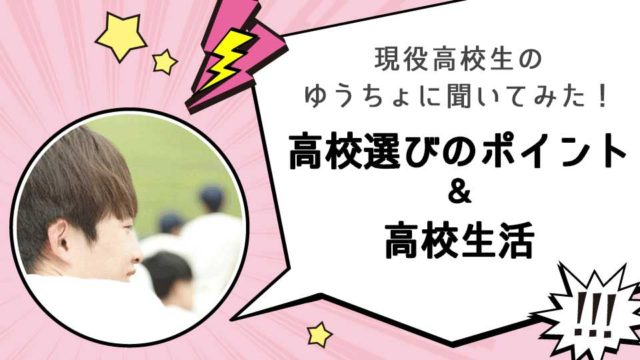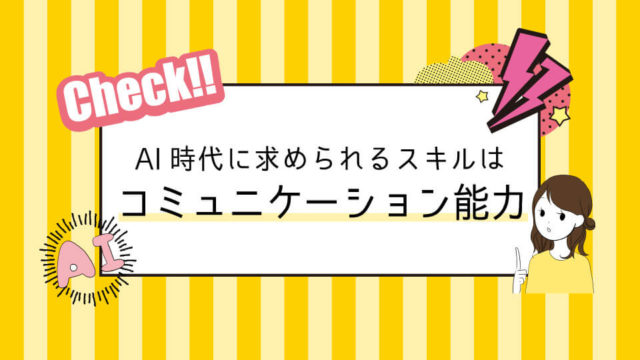挿絵:うみこ
こんにちは、るいるい(@Seayoumom1)です!
小学校でプログラミング教育が必修になるって知ってた?
必修ってことは、キミの街の小学校でもプログラミング教育が始まるってことなんだ。
でも、今さら聞けない質問「そもそもプログラミングって何?」っていうところからこの記事では紹介していくよ!
「プログラ・・?」の人も、「プログラミングできる!」て人も、生きていく上でこれからどんな力が必要になるかのヒントになるはず。
今回はブロガーでもありエンジニアでもある、ハニ太郎(@82_taro)さんのブログ記事から学んでいこう!
プログラミングは小学生から必要だ!
プログラミングってコンピューターの・・何かでしょ?と、ちゃんと説明できない人も多いんじゃないかな。
運動会のプログラムってあるよね。運動会で行われることが順番に書かれている予定のようなもの。そのプログラムと似ていて、コンピューターにさせたい事を順番に書いていくことをプログラミングと言うんだ。
コンピュータやインターネットの活用はこれからもっと進んでいく。IT化と言ったりするんだけど、これからますますコンピュータを使えること(人)が大切になってくるよ。
でも今はITに強い人が少ないから、小学校からみんなで勉強しておこう!というわけなんだ。

小学校のプログラミングは難しい言語を学ぶわけではない
ここで多くの方が勘違いされているのが、「プログラミング言語を習得することが目的なのでは?」ということ。
確かにプログラミング教育を通じて児童が言語を覚えたりすることは考えられます。
しかし、小学校でのプログラミング教育は言語の習得それ自体を目的としたものではありません。
あくまでコンピューターの活用事例や問題解決手法を学ぶことが目的なのです。
引用元:『ハニ太郎のもくもく勉強部屋』
「プログラミング言語」とはコンピュータが分かるコトバのこと。
なんか難しいことを小学校から勉強するのかな・・と思っていた人もいるかもしれないね。でも本当の目的は、「コンピュータがどんなところで役立っているか」を知ることや「問題を解決する方法」を学ぶことなんだ。
問題を解決する方法とはつまり、ゴールや目標から逆算して、ものごとを順番に計画し実行すること。このように問題を解決しようとする考え方のことを「プログラミング的思考」というよ。
これは日々の生活にも活かせるし、大人になって社会に出たときにも必要な力だ。
たとえば、小学校で習うプログラミングはこんな感じ。
- サイコロの上の面としたの面を足すと7になる
- 上の面が1なら下の面は6
- サイコロを同じ方向に2回転がすと、上の面はいくつになる?
これがプログラミング的思考。
頭の中で行動を予測し、想定するのがこの学習の基礎だ。
「国語」「算数」は「プログラミング」?
プログラミングは予測だ。
それは国語や算数にも使える。
例えば、「鮪」「鮫」「鯛」これは「まぐろ」「さめ」「たい」と読む。
じゃあ「いわし」ってどういう漢字だろう?
なんとなく「海にいるものだから魚へんがつく」と思ったはず。
プログラミング的思考があれば、「いわし」は海の生き物で、海の生き物の大半は魚へんがつく。だから「いわし」も魚へんがつく。
と想像に難しくない。

各教科の中で思考力や態度を身につける
漢字をいっぱい覚えることや計算を速くできることではなく、色々な教科の学習を通してさまざまな力を伸ばすことが一番の目的なんだ。
学びの姿勢や人間性の育成もプログラミング教育の目的の一つと言えます。
言うまでもなく、学びの姿勢や人間性は将来的に役に立つもの。
そういった姿勢を早いうちに身につけてもらうためにもプログラミング教育は有用なのです。
引用元:『ハニ太郎のもくもく勉強部屋』
なんか難しいこと言ってるけど、世の中のルールや規律って効率よくプログラムされてもの。
仕事もそう。
そのプログラム=規則性に気づくことができれば、新しい仕事を生み出したり、人の気持ちに寄り添ってより良い仕事を考えたりすることができれば、社会に出て活躍できること間違いなしだ。
プログラミングを体験する
教科の中では実際にプログラミングを体験することがある。
例えば音楽の授業で、音の長さや高さを変えて自分で音楽を作ったり、理科の授業で電気製品を動かしたり、というように、コンピュータに指示を出して動かす仕組みを学ぶ。
体験しながら自然とプログラミングが学べるように、どの教科にどのように取り入れていくかの具体的な計画は今のところ各学校に任されている。
すごく面白いし、ワクワクしながらその授業を待っててほしい。
まとめ
紹介したように、学校では教科の中でプログラミングを取り入れていくようだね。
でも身につけた力を発揮しないと活躍はできない。自分の強みや主張を発信するために、このミラブロメディアでは中高生のキミたちにブログを書くことをおすすめしてるよ。
学校では教えてくれない「ブログ」の魅力をこれからも発信していくからチェックしてね!